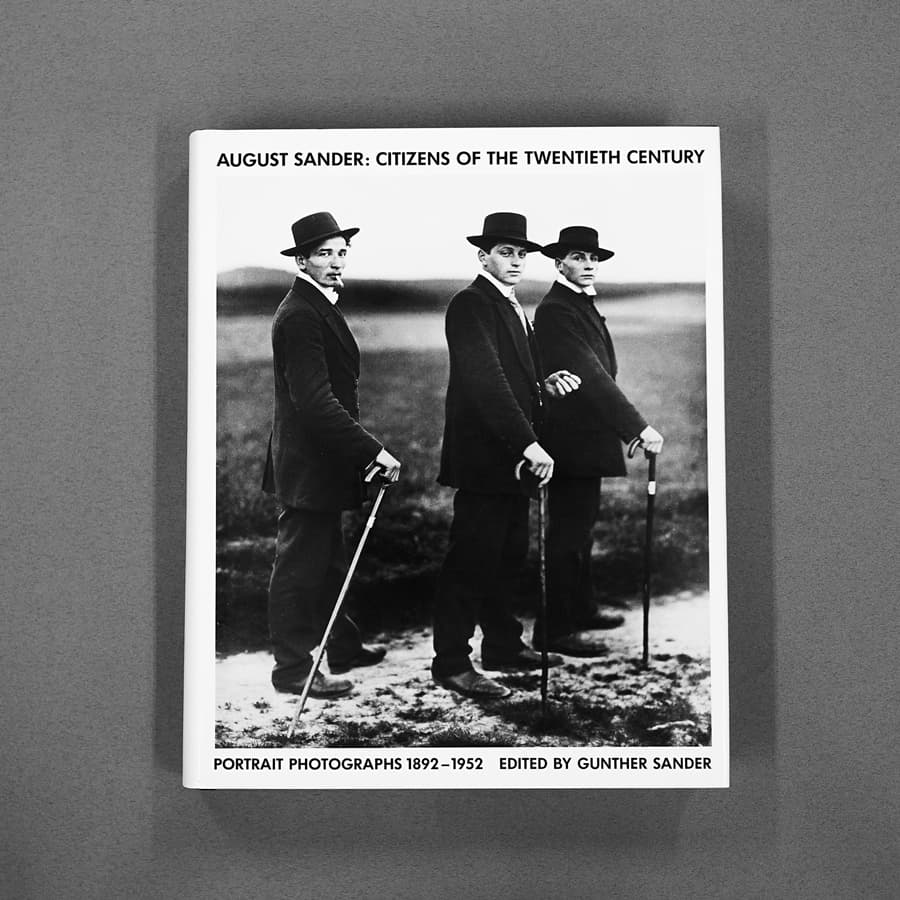The fusion of urushi and fashion by YOSHIROTTEN
漆芸家 桐本滉平とヨシロットンが手がける 漆とファッションの融合

数多のファッションブランドとのコラボレーション、霧島アートの森での個展開催など、グラフィックを軸にした多彩な活動を行うヨシロットン。彼がアートディレクターとして新たに手掛けたのが、日本が世界に誇る伝統工芸の漆と、日本のクラフツマンシップとイタリアの美意識が宿るタトラスのダウンアイテムを融合させるという斬新なプロジェクトだ。漆の表現技法の一つである「ぼかし塗り」をテーマにし、色のグラデーションはもちろん、光や陰影の移ろいも感じさせるようなグラフィックを生み出した。そのきっかけとなったのが、今回のプロジェクトのキーパーソンである漆芸家の桐本滉平だ。桐本は輪島塗で知られる能登半島の輪島で生まれ、代々に渡って漆にまつわる仕事に取り組んできた家系の八代目である。彼は漆芸の伝統に敬意を払いつつも、枠に捉われない新たな表現を探究し、国内外で精力的に作品発表を行なっている。ヨシロットンのクリエイティビティとタトラスのクラフツマンシップに大きなインスピレーションを与えた漆芸の魅力を探るべく、能登半島地震の爪痕が残る輪島の地で、仮設工房を設けて漆を塗り続ける桐本を訪ねた。

ー今回のコラボレーションに込めた想いを教えてください。
今回のコラボレーションは、2023年にヨシロットンさんと生み出したぼかし塗りの漆器をタトラスさんが目にし、新たなプロジェクトにしてくれたことがきっかけです。その一度のコラボレーションだけに終わらず、こうして次に繋がったことが素直に嬉しいです。「SAKAZUKI」と名付けたその漆器の盃は、ヨシロットンさんのアーカイブの中でも特に反響が高いようです。フィールドの異なる三者がコラボレーションする上で気をつけたのは、工芸は工芸として、アートはアートとして、ファッションはファッションとしてのアイデンティティをしっかり持ちつつ、互いが尊重し合うこと。どちらかに迎合したり吸収されるのではなく、バランスの取れた交わりをすることを目指しました。ヨシロットンさんが目指すぼかし塗りを形にするために、会話を重ねて何度も漆を塗り重ねましたし、そのぼかし塗りを服に表現するために、タトラスさんは何度も生地の開発や染色を試行錯誤してくれました。全員が対等に寄り添い合ったことで、漆も、グラフィックも、洋服もコラボレーションとしてバランスの取れた仕上がりになりました。時間をかけて会話を重ね、信頼関係が生まれたからこそでした。

ー表現で特に大切にしたことを教えてください。
やはり色ですね。漆の色は顔料で決まるのですが、まずはヨシロットンさんが世の中にある漆の色や顔料を頭にインプットしてくれました。そして彼が表現したい色を表現するために僕がサンプルを作っていきました。今回の最終アウトプットの指標となるのは、9000年前から存在し、今回も物理的に唯一無二となる漆の色でした。だから僕が作ったぼかし塗りを見本にしながら、生地に染色してみてはまた生地の細かなアップデートを行い、全員が目指す色を表現するためにタトラスさんは何度も時間とコストをかけてくださりました。ここまで付き添ってくれるのはすごいなと驚かされました。
ー「漆は9000年前から存在した」とのことですが、漆という言葉は誰もが知っていますが、漆とは何なのかがいまいちピンとこない人も多いのかと思います。日本における漆について教えてください。
諸説あるのですが、人間が漆を使い始めたのは縄文時代が起源だとされています。漆を加工して塗った武器やお守りが実際に出土もしています。漆はある一定の面積や体積を超えると、水にも虫にも、酸やアルカリにも負けない性質を持ちます。その性質に人間が気付いたのは、蜂の巣が木からぶらさがっているのに落ちないことに疑問をもった人が、蜂を追いかけ、蜂が木の幹から漆を採取していることを発見したからとも言われています。当時の縄文時代は食べるために狩りを主にしていたので、より強く長持ちする道具を作るために漆を加工し、矢の矢尻と柄を結びつける部分にコーティングとして塗り始めたのです。
漆の原液に直接触ると肌がかぶれてしまうのですが、それは傷や火傷のような外傷とは違い、かゆみが治った後には肌が新陳代謝したように生まれ変わります。そのエネルギーを縄文時代の人たちは感じ取り、儀式や魔除けのための道具にも漆を塗っていたようです。漆を塗った装飾品を身につけることで魔除けになると考えていたのですね。機能的なだけでなく、精神的にも漆は日本人の歴史と深い関係があります。

ー桐本さんが生まれ育った輪島は「輪島塗り」としても漆産業が有名ですが、輪島と漆の関係性を教えてください。
輪島塗の特徴は、漆や木だけでなく、下地となる珪藻土にあります。珪藻土とは珪藻(藻類の一種)の殻の化石で、珪藻土を漆に混ぜることで器が丈夫になるんです。珪藻土は海底の地層に堆積したものなのですが、輪島がある能登半島は地殻変動が活発なため、海底にあった地層が隆起して半島になっています。だから珪藻土を豊富に含んだ地層が地表に現れ、資源として手に取りやすいんです。何万年もの時の経過を経て命が結晶化した素材である珪藻土があるからこそ、輪島塗は漆器の中でも高い機能性を特徴として持つことができています。
また輪島塗は最大で124もの工程があり、工程ごとに職人が分業してリレーをすることで出来上がります。珪藻土や漆の原液の専門問屋さんも町中にあり、この土地の特性を活かした一大産業として、住民たちが一体となり作り上げるのです。だから素材や技術よりも、漆芸という目に見えないものをコミュニティーとして生み出している無形文化であることが輪島塗の価値だと思っています。

ー桐本さんがものづくりにおいて大切にしていることを教えてください。
漆は人間の生活に絶対に必要なものというわけではありません。ですが、あることによって生活が豊かになると信じています。世の文明は日々進歩しているかもしれませんが、人が人らしく生きることも同時に難しくなりつつあると感じます。ですが、生きることの最も中心にある衣食住にこそ心が感動する瞬間を感じていたいですし、その揺るぎないエネルギーを僕は求めています。1つのものを長く大切に使うことに豊かさを感じる人もまた増えていると思うので、より素朴で、どっしりと人間の生活に寄り添えるものを作っていきたいです。1人でどれだけ足掻いたところで大きく世の中を変えることはできないかもしれませんが、少なくとも僕の作品を手に取ってくれた現代を生きる人、未来を生きる人に豊かさを感じてもらえることを目指しています。
そのためには「作り手がどれだけ信念を持っているか」が大切です。僕にとっての信念は、「人間は自然の一部である」ということ。そう思うようになったのは、輪島という土地で生まれ育ったことがやはり最大の理由です。僕は漆芸を生業にする家系の8代目で、祖父も父も輪島で漆器を作っていました。明るい面だけでなく苦しい姿もずっと間近で目にしてきたからこそ、自分は漆をしたくないと幼い頃から正直思っていました。漆から、輪島から離れるために東京にある大学への進学を目指したのですが、上京して受験会場に向かうまさにその日に、2011年3月11日の東日本大震災が起こったのです。その瞬間は都内の駅にいたのですが、交通網は完全に止まり、慣れない東京で1人帰宅難民になりました。電話も繋がらないですし、初めて24時間以上起きていました。たまたま父も仕事で上京していたので無事合流はできたのですが、父の東京での売り上げもしばらくの間はゼロになってしまう状況。それは家族を養えないだけでなく、従業員の方にお給料も払えないということを意味します。それほど苦しくなるのであれば、いっそのことやめればいいのにとさえ正直思ってもいました。それでも漆をやめようとしない父や祖父は、一体どのような理由を抱えているのかと、自分の家族が心に持っている想いをきちんと考えようと思えたのです。

ー家族が代々取り組んできた漆芸に向き合うきっかけになった東日本大震災や、輪島塗りの大きな特徴である珪藻土は地殻変動が盛んな能登半島だからこそ豊かであるなど、自然環境が桐本さんにとって重要なきっかけになっていますね。
結局は自分で人生の選択をするわけですが、人間や自然を滅ぼすかもしれないシステムに加担する可能性があるとすると、少しでも自然に寄り添える仕事をしたいと強く思いました。それは東日本大震災のときの原子力発電も大きな要因です。これだけ自分の家業が代々続いてきたのは、周りの人や自然との関係や想いをずっとバトンタッチしながらリレーしてきたからこそなのだと気付いたのです。それから考えは一転して、漆芸という家業に関わりたいと言い出すようになったんです。文句を言ったり、絶望しているだけではなく、自分なりの希望をもって、未来に、後世を受け継ぐ人たちのためになる生き方をしないといけない。僕の場合は家業である漆芸でしたが、誰しもがそのように思える仕事や希望を見つけられると、大袈裟ではなく世界は平和になるのだと思います。過去の歴史と未来の希望のバランスを考えることが、現代を生きる人の責任ではないでしょうか。


ー漆に向き合ったことで見えた、桐本さん自身が漆に見出す可能性を教えてください。
漆器は100%自然の素材だけを使って作ることができます。だからこそ、漆の未来は扱う人間にかかっているとも言える。できるだけ自然を壊さず、むしろ人間が自然の一部となって存続していくために軌道修正を意識することが大切ですし、その再確認のきっかけに漆器を使うという選択がなれると信じています。自然界の動植物は弱肉強食ですが、それは自然をコントロールしようとすることではなく、むしろ自然界の調律ですよね。人間だけがその生態系から外れつつあるからこそ、意識的に自然界と調和を目指す必要がある。人間が漆と付き合い続けられる間は、まだ人類も地球も豊かに存続できているという証明でもある。そう信じて僕は漆に向き合っているのかもしれません。漆芸は自然の素材のみを使うからこそ、気温や湿度、気圧の変化はもちろん、季節の変化や月の満ち欠けにすら影響を受けます。どれだけ時間を過ごしても、自然現象とも言える漆を理解し切ることはできない。だからこそそんな漆を通じて自分の中で祈りを捧げることが、僕が漆を扱う理由、自然の一部になろうとしてるということなのかもしれません。
9000年前の縄文時代を生きた人々は、祈りを捧げながら漆を用いた。9000年後の現代を生きる桐本もまた、願いを込めるように、漆の新たな歴史を重ねるかのように漆を何層も何層も塗り重ねている。文明がどれだけ発展しようとも、人間の本質は普遍なのかもしれない。人間と自然の間に本来は境界線などなく、地続きの世界であるはず。過去も現在も未来も、時の流れとともに溶け合いながら続いている。世の中のすべてのものには、実は境界があるようでないのかもしれない。そのことをヨシロットン、桐本、タトラスの三者のコラボレーションは体現しているかのようだ。
| Photo Yuki Hori | Interview & Text Yutaro Okamoto |