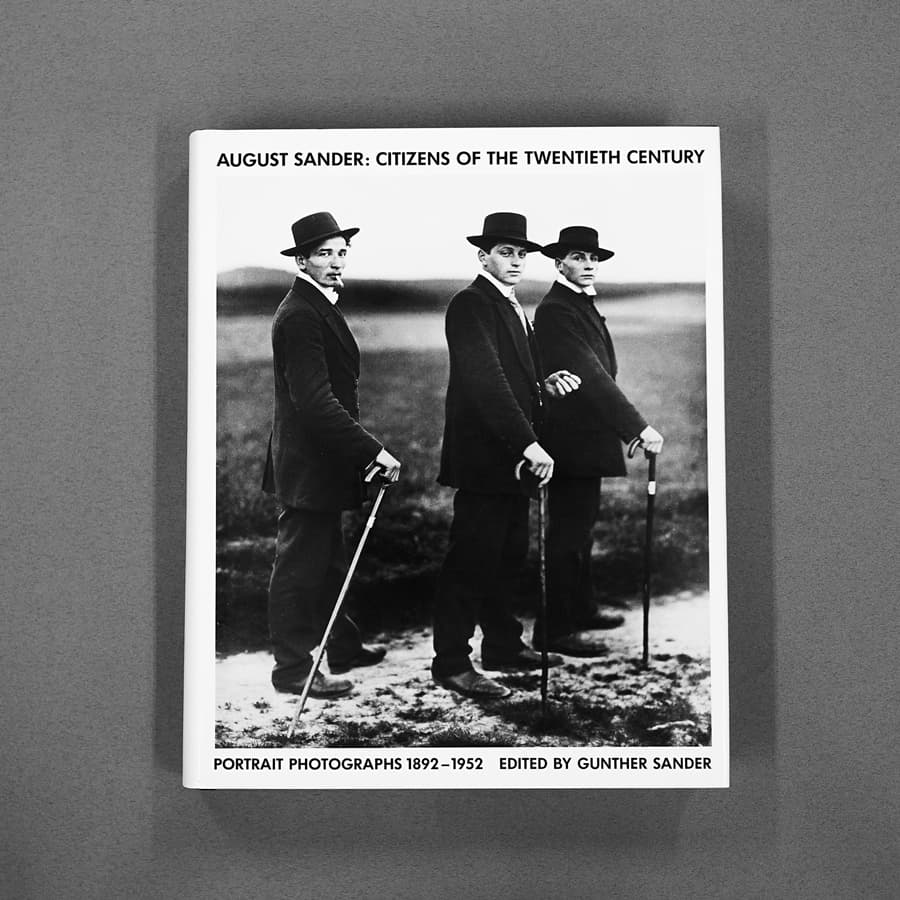Photography to the future by Tsuyoshi Noguchi
スティルライフの 教科書

2. Cranium Architecture (1989)
3. Still Life (2001)
この写真集に出会って物撮りが
面白く感じるようになった
野口強
野口強が語り継ぐべき写真集について案内していく当連載。今回はスティルライフ(静物写真/物撮り)におけるマスターピースについて話を進めていく。20世紀を代表するファッションフォトグラファーのアーヴィング・ペン(1917-2009)。現代のファッションフォトグラファーに多大な影 響を与えた人物として知られているが、彼は元々、画家を目指し美術大学で学んでいた。そして、雑誌『VOGUE』で当時アートディレクターを務めていたアレクサンダー・リーバーマンから誘われ、同誌で働き始め、表紙のデザインを担当することからペンのキャリアは始まったことが知られている。写真はリーバーマンからの勧めで、ペン自らで撮り始めたことがきっかけである。長いキャリアの中でファッション写真のみならず、ポートレートやスティルライフも幅広く撮影した。
「商業写真を多く撮っていたペンだから、撮り溜めてきた写真の数が多かったということもあるかもしれないけれど、これだけの枚数のスティルライフがある写真家というのはほかにいないと思う」と野口が語る通り、今回紹介した『Still Life』のように1冊すべてがスティルライフでまとめられた写真集というのは数多く存在するものではない。だからこそ、野口をはじめとする後世のクリエイターたちに多大な影響を与えているのだろう。ファッション広告における撮影というとモデルカットが一般的だが、対象物によってはモデルではなくスティルライフで見せるというのも手法の1つである。野口もこれまでの仕事の中で、多くの物撮りをしてきたという。
「スタイリストになりたての20代の頃なんかは、物撮りというと恐怖の存在でしかなかった。当時はカタログのような作りの雑誌が多かったから、ネクタイだけを何本も変えたVゾーンを撮り続けたり、501®のジーンズを何本も集めて切り抜きの写真を撮ったりというのが物撮りの印象だった。でも当時、ペンの写真を見た時に、物撮りでありながらも作品のような写真が撮れるもんなんだと気付いた。物撮りでもこんなことができるのか……と思った。これは、ファッションの提案としても物撮りで見せることは面白いんじゃないかと思って自分でも始めたね」とペンのスティルライフに出会った当時の思いを語る。ペンの写真から影響を受け、ジュエリーのようなものを対象物として扱う企画の時には特に物撮りを選択することも多いようだ。「撮影するものがウォレットチェーンだったら、それを身につけたモデルの腰元を撮るのが一般的かもしれないけれど、そういうビジュアルはすでにありふれていて、どこかで見たことのある印象になってしまう。それであれば、物撮りで見せた方が面白くて強い写真になるんじゃないかと考えることもある。今までも、あるラグジュアリーブランドの企画で、蛇とバングル、秋刀魚とチェーンを一緒に撮影したりしてきたけれど、そういう物撮りで見せるのはやっぱりペンの影響だと思う。まさに、ペンのスティルライフは教科書のような存在」と話す。自らを「ペン好き」と語る野口は、写真集はもちろんのこと、プリントも数多く所有してきた。スティルライフのみならず、ポートレートやファッション写真も格別だという。そもそも、野口にとってペンのスティルライフはどのような部分に惹かれているのだろうか。

絵画のようにものを構成した写真から道端で拾ってきたタバコの吸い殻のような写真まで色々とあるけれど、どれをとっても強い写真であるというところに惹かれるんだと思う。唇に蜂が止まっている写真なんて、生きた蜂なのかどうかわからないけれど、どうやって撮っているのかなって思うよね。良い写真がたくさんありすぎて一番が選べない。写真集もいいけれど、プリントが本当に綺麗なんだよね。こうやって改めて見ていると、いくつかすでに手放したプリントがあるから、手放さなきゃ良かったなって思えてくる」と笑いながら話すが、ピカソを撮影したポートレートや唇についたチョコレートを舌で舐めとる瞬間を撮影した“Chocolate Mouth”を今でも所有しているというから驚きだ。モデルカットよりも、シンプルでいて表現の幅が豊富なため、ある意味、正解の見えづらいスティルライフ。だが、教科書のような存在のペンの“Still Life”には答えが詰まっている。

野口強
1989年から、スタイリストとして長年国内のファッションシーンを牽引し続ける。ファッション誌や広告を中心に活躍し、多くのセレブリティからも信頼が厚い、業界の兄貴的な存在。ネットショッピングが普及している今でも、写真集は状態を確かめるため実際に書店で確かめてから購入している。
| Photo Masato Kawamura | Interview & Text Takayasu Yamada |