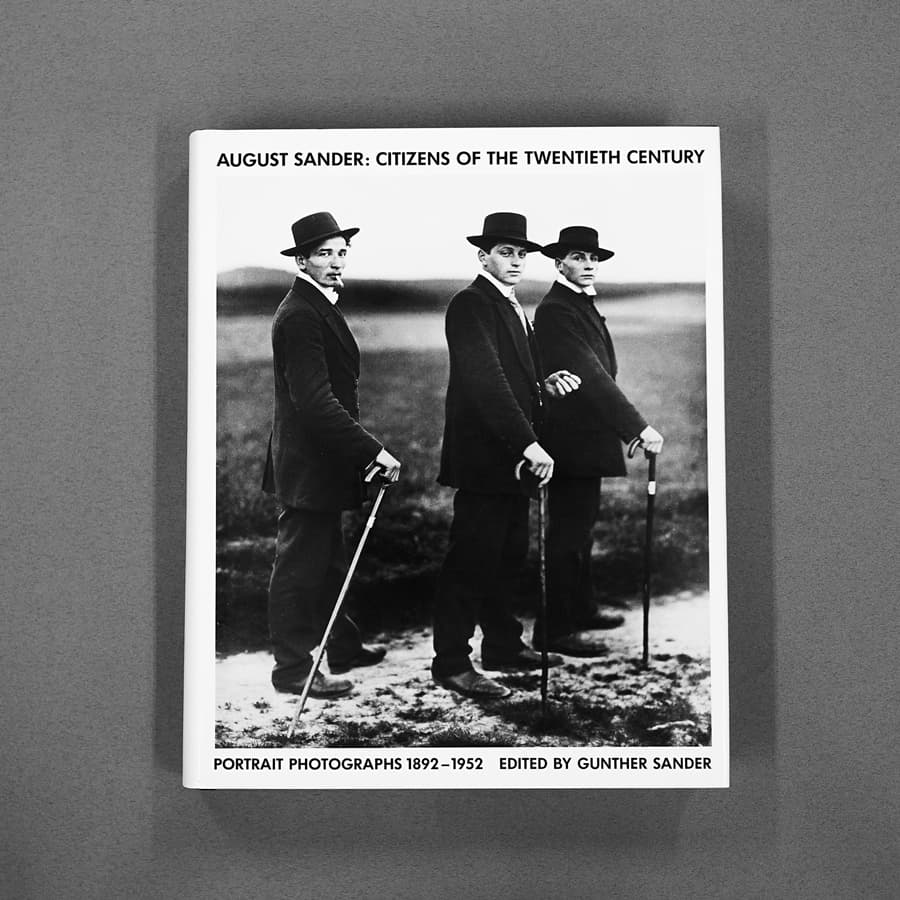Travel through Architecture by Taka Kawachi
柳宗悦が創り上げた 民藝のための建築

日本民藝館
休館日 毎週月曜日 03-3467-4527 mingeikan.or.jp
生活の中で実用品として使われているものに美を見出し、それを世に知らしめるという「民藝運動」を創始したのが柳宗悦(やなぎ むねよし)という人だ。柳の収集品は当時の美術界では注目されることがほぼなかった道具として用いるために作られた陶磁器、染織、漆器、木竹工などが中心で、それらを展示する場として創設されたのが東京·駒場にある「日本民藝館」なのである。現在この建物で見ることのできる展示物は、時の経過と民藝に対する人々の意識が高まったことで、どれも由緒あるもののように目に映るが、なにしろ大半は実用品を収集したものだったがゆえに、秘められた美しさを伝えるために柳は一際洗練された展示施設に仕立てることを目論んだはずだ。
柳の設計による木造2階建の旧館は1936年に完成。それに加えて1983年に鉄筋コンクリート造りの新館が増築され、内部で本館と新館が繋がった展示空間を形成している。一階の外壁には石材が貼られ、二階部分は漆喰による白壁、各展示室も和風建築の意匠を基調としながらも、必ずしも純和風とは言い難いものを取入れた造りとなっているのが特徴だ。民藝館の外観が土蔵を想わせるのは、「なまこ壁」と呼ばれる日本独特の壁塗りの様式で覆われているからで、内装にいたっては木製の柱や梁、磨き上げられた床板、壁も漆喰に覆われていて、ここは紛れもなく日本の伝統建築の様相なのである。当然、柳が提唱した“用の美”を展示するのに欧米風の無機質な建造物などはそぐわないと考えたのだろうが、「美術館というより豪農の古民家みたいだな」というのが個人的な最初の印象だった。

ところが、ここの外壁や門や土間に「大谷石(栃木県宇都宮北西部の大谷一帯で採れる緑色凝灰岩)」という聞き覚えのある石材がふんだんに使われていることを知るや、俄然この建物の見え方が変わっていったのだ。栃木県産の大谷石が使用された最初の有名建築がフランク・ロイド・ライトが手がけた「帝国ホテル」である。大谷石の風合いにライトは魅力を感じ、建築に大胆に取り入れたことで、それ以降、新しい建材として国内の洋館やモダン建築に大谷石は多く使われるようになっていったのだ。それとはまた異なった個性を持つ大谷石建築がこの民藝館というわけだが、耐火性と防湿性も高く展示施設に向いているという点でも魅力だったのかもしれない。大谷石が引き金となって新鮮な目線で館内を見始めると、どうやらここはかなり癖のある建物であることがわかってきたのだ。


日本民藝館の特徴が顕著に現れているのが、玄関からすぐ眼前に広がる重厚な「両階段」である。洋館やオペラ座などで見かけるような中央からY字に分かれる仰々しい階段で、吹き抜けのエントランスホールにおいてインパクトのある雰囲気を漂わせている。その階段を登りこじんまりとした各展示室に足を踏み入れると、紙障子による採光こそ和風であるものの、柳がデザインした陳列ケース(ちなみにこの展示ケースと建具に総工費の半分を使ってしまったという)が、仄暗い木調の展示室と調和しどこか無国籍風だったりするのだ。ケースの中の展示品に目をやると、ごく小さな板紙に手書きでのタイトルのみで説明文がない。その理由は、知識よりも先に直に展示品と向かい合うべきだという柳の信条に基づくものであるからだという。
……と、ここまで書き綴ってみたものの、日本民藝館が近代建築の範疇で語っていいものなのか今も確信を待てないでいるのも事実だ。しかし宗教哲学者で文筆家で収集家であった柳宗悦による世に存在する「作品」として見ると、かなり興味深いものであることには間違いない。日頃からツイードスーツやホームスパンのジャケットを着こなし、バーナード・リーチとの交友や英国の家具を柳が愛好していたことを踏まえれば、この民藝館に外来の要素が随所に見られるのもわりと自然なことだったのだろう。ゆえにここを訪れる際には、柳の美意識が隅々まで投影された唯一無二の「民藝建築」であることを意識することで、より面白みが増すのではないかと思うのだ。
日本民藝館
mingeikan.or.jp
河内タカ
長年にわたりニューヨークを拠点にして、ウォーホルやバスキアを含む展覧会のキュレーション、アートブックや写真集の編集を数多く手がける。2011年に帰国し主にアートや写真や建築関連の仕事に携わる。著書に『アートの入り口アメリカ編&ヨーロッパ編』、『芸術家たち 1&2』などがある。
| Text Taka Kawachi | Photo The Japan Folk Crafts Museum | Edit Yutaro Okamoto |