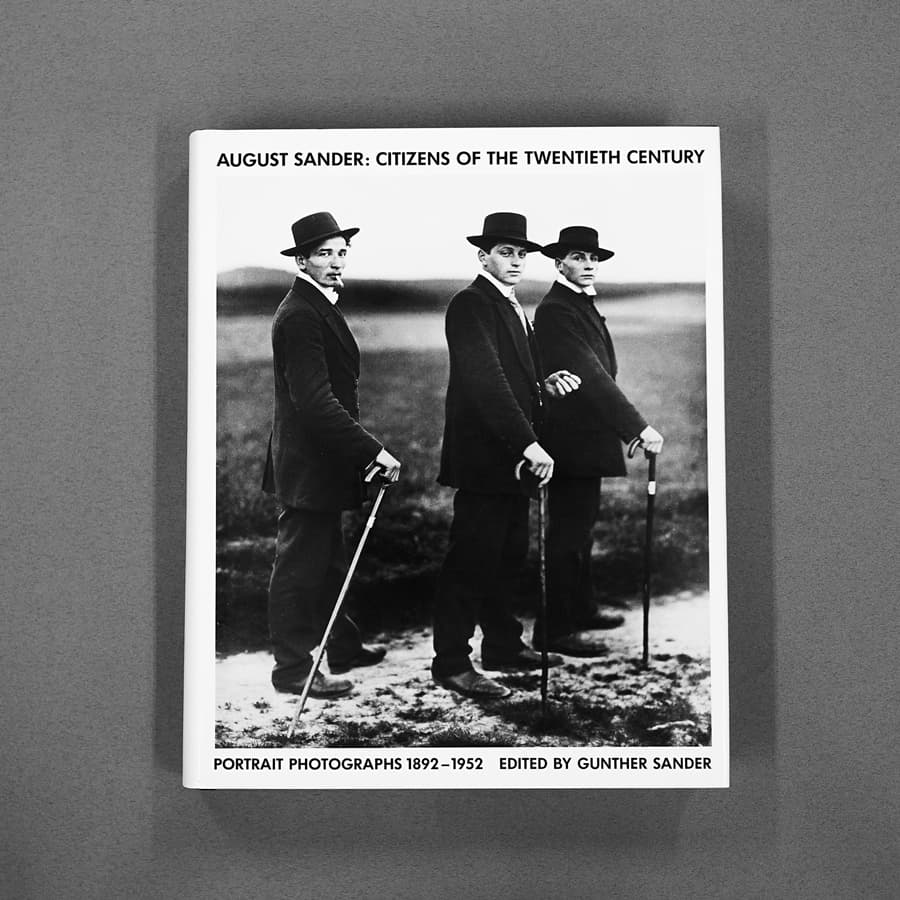ART & CRAFTS Black Pottery RANDO ASO
プリミティブな手法と モダンな彫刻アプローチ

一見正反対に見える
アプローチの組み合わせ
見る角度によって表面のテクスチャーや光の反射で表情を変え、その重厚さも相まってまるで鉱物を削り出した彫刻のような作品。だがその正体は陶器だというから驚きだ。手掛けたのは岐阜県美濃加茂市で制作活動を行う阿曽藍人。まずは彼のインスタグラムに投稿されている動画を見てほしいのだが、野焼きで作品を焼いている姿に衝撃を覚える。野焼きという縄文時代の原始的な焼成技術を熟知する阿曽は、野焼きの低火度焼成を応用し、同じく低火度の灯油窯を用いることで今回の黒陶を生み出したという。その仕組みは後ほど記載するが、まずは本連載のナビゲーター 南貴之に阿曽の作品の魅力を聞いた。「これは何なんだ、と驚きましたね。素材も製法もまるでわからない。彫刻的で、空間に対してミニマルにアプローチすることに興味のある人なのかと思いました。だから窯焼きで造形を突き詰めているのかと思ったら、まさかの野焼きというプリミティブな手法に由来するものだった。原始的な手法とモダンな彫刻的アプローチという一見正反対に見える要素が組み合わされていて、アート&クラフツと呼ぶに相応しい作品です(南)」。
工芸的なアプローチから
想像力を刺激したい
焼成は粘土に硬度と色調を与え、陶器にするために非常に重要で神経を使う作業。昔は窯に数日間付きっきりで焼き上げられていたが、今では安全で操作の簡単な電気窯も主流になっている。だがその焼き方に物足りなさを阿曽は感じていたようだ。「大学の授業で焼き物を習っていたのですが、電気窯やガス窯で焼くわけです。でもなにか手応えのなさを感じていました。そんななか考古学の授業で野焼きを体験した時に、初めて自分でものを生み出した感動を覚えたんです。それからどんどん野焼きに魅了されていき、今に至ります。当時は土器を作っていたのですが、並行して彫刻的で空間にアプローチする作品も作っていました。その一部が今回の作品です。例えばこの箱型の作品(ページトップ、ページ下部左)は、箱という内側の見えない形状が想像力を働かせ、実際に蓋を開けてみたいという気持ちを促します。実際に蓋を開けてみると中に空間はない彫刻作品ですが、箱を開け閉めするための造形は工芸的なアプローチを応用しています。機能性をきっかけとして、想像力を掻き立てるものを作りたかったんです。球体とくぼみの作品も似たアプローチです。くぼみがあって器的な機能があるように見えつつ、球体を入れることでくぼみをなくしてしまう。するとくぼみが持つ意味も変わってくるんです(阿曽)」。
原始的な手法を応用した黒
空間へのアプローチを第一にするからこそ、観る者の造形へのフォーカスを強めるために色は漆黒に仕上げているのだと気づく。この漆黒は一体どのようにして生まれるのか。「黒陶を作るためにはいろいろな方法があるのですが、僕はまず作品を窯で焼き、800度ほどの高温状態で窯から出し、 籾殻(もみがら)と一緒に地面に埋めるんです。作品は800度の高温状態なので、周りを覆った籾殻は燃え始めます。そして燃えて出てきた煙や煤が作品表面の隙間に入り込み、温度が下がるとともに隙間が小さくなって炭素が吸着するのです。土の表層から内部に色が染み込んでいくため、このように深い黒になります。艶に関しては、焼成の前に作品を磨くことで生まれています。ピカピカの泥団子を作るように表面を磨き上げていくんです。でも色も艶も焼成の温度が上がりすぎると失われる。野焼きや黒陶だからこそ生み出せる色なのです」。阿曽の作品は近づいてよく見ると、磨き上げるときについた手の痕跡や籾殻の擦れ跡が残っている。人の手の温もりが感じられる造形や黒の仕上がりだからこそ、本能に訴えかけてくるような原始的な強さを持っている。

Right Top to Bottom
Width 475mm Height 200mm Depth 185mm
Width 490mm Height 250mm Depth 470mm
阿曽藍人
1983年、奈良県生まれ。現在は岐阜県美濃加茂市で活動。野焼きを用いた黒陶の彫刻的作品は神秘的とも言える輝きを放ち、ロサンゼルスのノナカヒルギャラリーで展示されるなど国外からの注目度も高い。
南貴之
アパレルブランドのグラフペーパーやフレッシュサービス、ギャラリー白紙など幅広いプロジェクトを手掛ける。今年1月にはアムステルダムに支社を作るなど、海外での活動にも力を入れている。
| Select Takayuki Minami | Photo Masayuki Nakaya | Interview & Text Yutaro Okamoto |