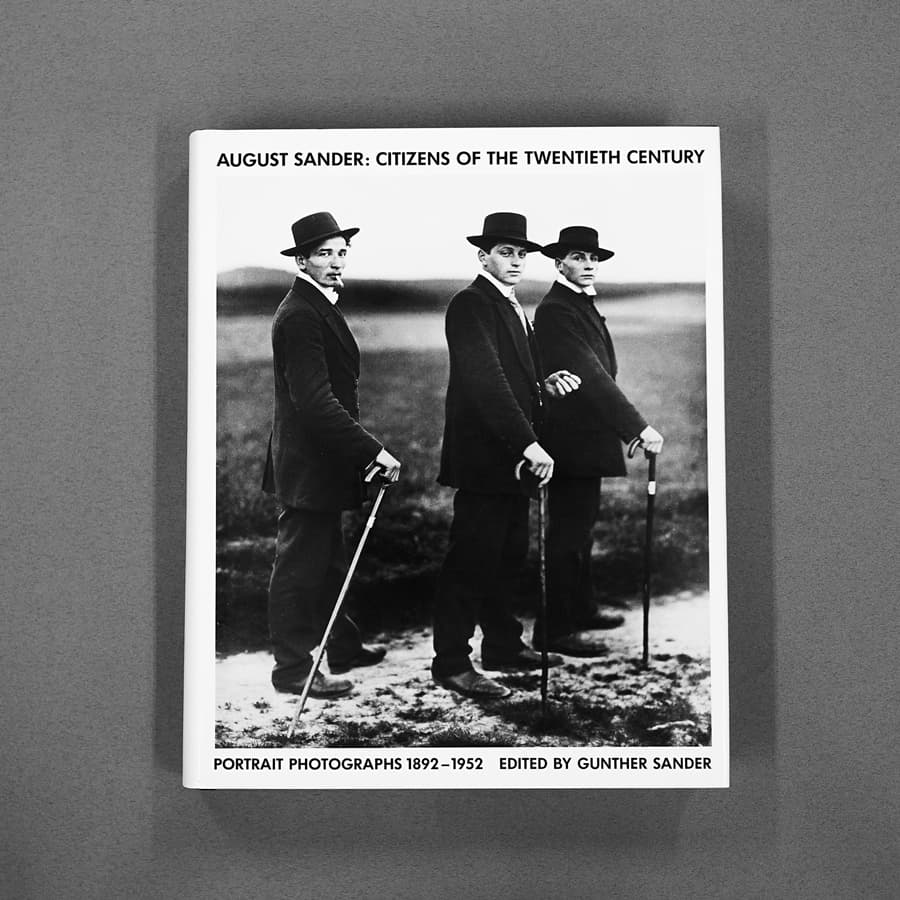The Roots of Japanese Colors
書道家 新城大地郎と考える 日本で大切にされてきた色

新城大地郎
色は生き物のように表情を変える
日本の色の始まりは「クロ」、「アカ」、「シロ」、「アオ」の4原色と言われ、それは一日の陽の光の移ろいに由来する。「クロ=暗い」、「アカ=明るい」、「シロ=顕し(しるし。はっきりしているの意)」、「アヲ=漠(顕しの対義語。はっきりしないの意)」が語源だ。黒の対称は白だと思いがちだが、それは西洋をルーツにする考え方であり、古代日本では黒の対称は赤であり、白の対称は青とされてきた。奇しくもこの4原色をキーカラーとして扱う人物が思い浮かんだ。書を表現の軸にするアーティスト 新城大地郎だ。彼は墨で書道用紙に黒と白の世界を書き、赤紙の書の作品や、故郷 宮古島の伝統工芸品である宮古上布を染める藍染めの色をオマージュした青いダルマのシルクスクリーンを制作。自然豊かな宮古で感性を研ぎ澄ませる新城だからこそ、この4原色を本能から選んでいるのではないか。新城が考える日本らしい色を聞いた。「小さい頃から墨を使って文字を書いてきたので、黒は無意識にもずっとそばにありました。だから黒を色として捉えたり、意味を見出すようなことはあまりしていなかったです。でも作品が物理的に大きくなっていくにつれて使う墨の量も増えるようになり、新たな黒が見えてくるようになりました。墨が定着する対象が書道用紙なのか、藁半紙なのか、キャンバスなのか、はたまた木なのかとメディアによって墨の表情は変わってきます。真っ黒に見えるようで、合わせるものによって色が変わる。まるで生き物のようです」。

Right 宮古の伝統工芸品である宮古上布を染める藍染めからインスピレーションを得て作った青いダルマのシルクスクリーンプリント。濃淡の異なる二色の青で擦り上げられている。黒に近い藍色が宮古の藍の特徴である。
色気=感覚を揺さぶるもの
幼い頃から黒に触れ続けてきた新城だからこそ見える黒の世界がある。水墨画には「墨に五彩あり」という言葉があり、墨の濃淡や階調の違いで色を感じさせる世界を表現するが、新城が言う黒の色とは、“色気”を意味している。「数年前から自分で墨を作るようになりました。煤(すす)と膠(にかわ)を混ぜ合わせたノンケミカルな墨です。まるで自分の感覚や気持ちの揺れが乗り移った生き物のようであり、“色気”を出していると感じます。機械で作られた化学的な墨は使いやすくて腐りにくく優秀ですが、色は均等で奥深い表情も出しづらい。それは素材だけの話ではなく、作り手の思いがストーリーとして込められているかどうかということも含んでいます。わかりやすいものよりも、いびつでも作り手の気持ちが伝わるもの、感覚が揺さぶられるものにこそ色気は宿ります。そこに人は何かを求めるわけですし、日本の色にはそんな色気があると思います」。化学的な計算式と機械によって作られた墨と自分の感覚を頼りに手作業で生み出した墨では、黒は黒でも全く異なる色となる。それは単なる黒さの話だけではなく、溢れ出る色気=オーラなのだ。日本は天然素材を用いた染料や顔料で色を表現してきた歴史と文化を持つが、そのような色に日本らしさを感じるのは新城が話す“色気”があるからなのだと腑に落ちた。
赤は生命力を
青は洗練された美しさを
黒にも色があるというのは色気のことだけでなく、新城が使う墨を例にしても赤い黒や青い黒があるという。赤と青は日本の原色として冒頭に挙げたが、感情に強く訴えかける力を持つからこそ、日本の始まりの色となったのではないか。新城も墨を通じて色の力を感じ取っているようだ。「墨は製法や乾燥の年数によって赤い黒や青い黒になります。赤や青で黒を表現しているのはおもしろいですよね。墨を長年使っていると、青っぽい黒だなとか赤っぽい黒だなとわかるようになってきます。
赤は血の色ですから、エネルギーや生命力がありますよね。縄文土器のような、内側から力が溢れ出てくるプリミティブなイメージです。青はより繊細で、弥生土器のような洗練された美しさを感じます。人の状態や気分を判断するときは、その人の顔の血色を見ますよね。顔が赤くなっていたり、青ざめていたり。生きているとは血が動いているということなので、赤と青は生命に直結する重要な色なのです。
赤い墨の書き心地は、重たい筆で力強く書いているような感覚です。対して青い墨の書き心地はなめらか、静的なイメージです。僕は現在の作風においては赤い墨を使うことが多いです。墨を使い続けてきたことで黒の世界の奥へ奥へと踏み込んでいっている感覚があります。でも暗闇の中には光があるように、どんどん新しい黒が見えるようになってきている。黒は宇宙やブラックホールのように無限大の色なのです」。


光と陰影の美意識
黒の中にも色がある。闇の中にも光がある。会話の流れから「光」という言葉が新城の口からこぼれたが、それは「日本の色の始まりは一日の光の移ろいに由来する」という今回の企画テーマに偶然にも回帰した。「光によって色やものが見えるわけですが、あえてはっきり見せないことで生まれる意味もあると思います。黒は全てを隠すことができる色でもあるので、時代とともにわかりやすさを追い求め続ける世の中に対するアンチテーゼとして僕は黒を使っているのかもしれません。動かないと見えない、光の角度を変えないと見えない黒に色気を感じます。僕が生まれ育った宮古は太陽の光が強く、光に対して身体的に敏感になります。雲の動きで影が大きく形を変え、建築も庇が長いので影が伸びる。つまりは光と陰影の関係性。そのことを日本らしい感性としてもっとも象徴的に書いたのが谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』ですね。谷崎は漆器の美しさは闇の中でこそ見えてくると説いたわけですが、色気を感じ取ることが日本の色の美意識なのだと思います」。はっきりとは見えない曖昧な世界。闇から光へ、赤から青へ、晴れから雨へ。豊かな自然と四季に恵まれている日本では、ゆっくりと、しかし確実に日々変化していく自然のグラデーションに触れている。そんな環境が色気を見出す色彩感覚を育んできたと感じた。


新城大地郎
1992年、沖縄県宮古島に生まれる。幼い頃から禅や仏教に親しみながら書道に向き合い、型に囚われない自由で力強い表現活動を行う。禅僧かつ民俗学者であった祖父の岡本恵昭との共作の作品集『SUDIRU』を刊行した。
| Interview Photo Shono Inoue | Interview & Text Yutaro Okamoto | Special Thanks M1997 |