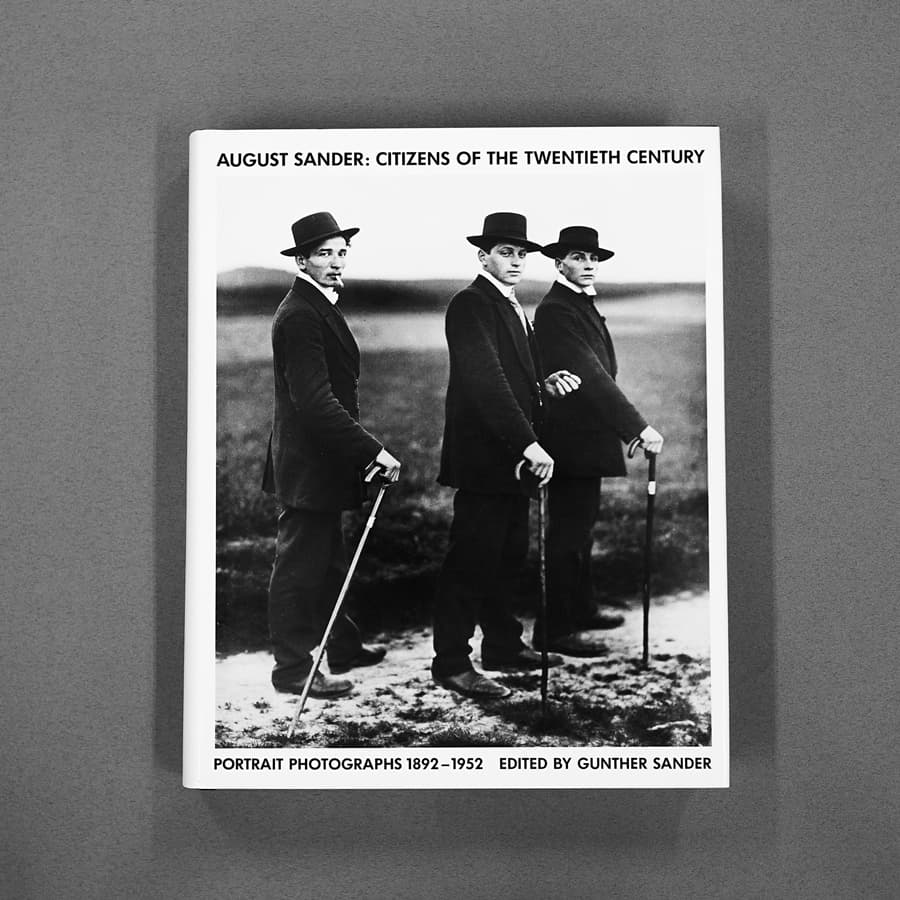Interview with Toru Watarai (IKEBANA artist)
いけばな教授者 渡来徹が考える いけばなの根源的な魅力
心の豊かさ

人の想像力を刺激する
渡来徹
生命の芸術として昔から愛されてきたいけばな。華道とも呼ばれるこの人間の営みは、常磐木を神の依代としてたてた行為や仏前に備える供花に由来するとされる。現在では2000~3000もの流派があるとも言われているが、草木の命を拝借し、人の手によって器にいける軸は変わらない。いける者も鑑賞者も、その一杯にさまざまな思いを巡らせるクリエイティブな活動だ。
この日本発祥の伝統芸能の魅力を後世にも残さんと活動するのがいけばな教授者の渡来徹。いけばな三大流派の一つである小原流で学んだ渡来は、現在は「Tumbler & FLOWERS」といういけばな教室を主宰している。一方、彼の独創的な作品や表現力は業界の垣根を超えて注目され、ファッションとの繋がりではロエベと協業で、ワークショップや装花を行ったりもしている。
伝統の枠に捉われず、現代におけるいけばなの可能性を広げる渡来。いけばなとは言わずとも、誰もが暮らしの中で花を目にし、触れ合う時間に豊かさを感じている中で、その道を極めんとする渡来は花をいける本質をどう捉えるのか。



環境を受け入れ
足るを知る
渡来が住むのは神奈川県鎌倉市二階堂。観光客もまばらな細い路地を抜け、湿度の高い鎌倉の気候と生い茂る緑、そして近くにある古刹が神秘的な雰囲気を醸し出す一角にアトリエを構えている。取材で到着するやいなや、「まずはいけるための花材を探しに行きましょう」とアトリエのすぐ裏手にある山へと案内してくれた。
「自分の足を使って出逢った花をいけたいんです。花道家として花をいかすというのは、自分の目で野にある花を見極め、切り取り、場に、器にいけること。そしてこの一連の作業に責任を持つということ。だからこそまずは、主たる花材にしっかり向き合いたいのです。基本的に植物は土地に根を張り動きません。そのため長い年月をかけて周辺の自然環境に適応し、進化してきました。こうして今日私たちが目にする多様な姿ができあがっているのです。今いる山と一つ先の山のわずかな風土の違いを植物は敏感に感じ取り、多様化してきた。だから土地と植物は切り離して考えることのできない関係なのです。これを尊重することが、花をいかす上で何よりも大切だと考えています。目の前にある事象を受け入れ、ないものねだりはしない。
“足るを知る”という言葉もありますが、花をいけているとつくづく実感します。いけばなを通じて土地や風土が色濃く現れるとするならば、私がどう形にしたいかではなく、花材がどのように育まれてきたのかを知ることが優先事項となります。今回いけた花材はどれも、その伸びやかな姿に惹かれて裏山で採ってきたもの。いけばなにするにあたり、山で感じた生命力の強さを器の上で表現したかったのです。陽の光を求めてほかの樹に絡まりながら伸びた藤ヅルの貪欲さ、生長過程の紆余曲折が想像できるユニークな朽ち枝、そしてはち切れんほどに赤く実ったヘビイチゴ。この一杯は、“鎌倉二階堂の花”と呼べるかもしれません。この一杯が鑑賞者それぞれの経験や感受性に照らし合わされることで、土地から解放され、花材という枠をも超え、人間の本能的な意識世界への入り口になると思っています」。
何を取るのかではなく
何を残したいのか
渡来が今回のためにいけてくれた“鎌倉二階堂の花”。その花材を求めて裏山を歩く彼の足取りは軽く、何かを感じ取っては立ち止まり、茂みに分け入っては花材を収集していた。そうやって自分の足で稼いで見つけたからだろうか、器へいける時間は迷いの表情を見せない一瞬の出来事だった。「自分ができることといえば、場所と光の方向性、器とのバランス、そして花の正面性を見極めて留める、その落とし所を見つけるぐらいなんです。最適解はひとつではありませんが、在るべき姿はすでに存在している。そこに向かって少しだけ自分の手を入れる感覚です。生かしたい部分が見えているから、その妨げになるものを取り除く。大切なのは何を取るかではなく、何を残したいかの見極めです。
いけた花に結果として自分の気配が現れることはありますが、いけばな作品において自己表現をしたいわけではない。たとえ独りよがりに自分の花を見せようとしたところで、主たる花の魅力は引き出せません。植物は重力に抗うことで光に近づけることを知っている。移動できないからこそ、種が落ちた環境に最適化すべく、最小限のエネルギーで最大限の効果を発揮するように生長します。だからそこには自然の機能美が備わっている。この美しさを損なわないよう器にいけるのが最も重要だと考えています。この機能美といかに折り合いを付けるか、その判断の違いが作風として現れるのだと思います。
『そこまでするのか』と誰かが感じるいけかたが、当人にとっては自然な姿かもしれない。ただこれは感性の違う他者への感想であり、植物の多様性同様に環境に育まれた結果です。だから私たちは自分にとって心地のいい落とし所を探すことに注力すればいい。何を大事にするかは人によって様々。その微妙な差異がグラデーションとしてあるからこそ、流派だけでも3000あると言われるほど多様化したのでしょう。そもそもいけばなが定まったのは600年ほど前の室町時代中期、池坊が確立させたと言われています。それから時代と共にさまざまな流派や花型が生まれてきました。それを踏まえて今を生きる身として心掛けているのは、自分が納得のいくものをいけ切るということです。その美意識やバランス感覚などはふわりと頼りない存在かもしれません。そんな時は自然として完成された植物の美しさに身を任せるんです。そしてその機能美にプラスアルファできる可能性として、人間が手を加えていくいけばながあると信じています」。
空白を作り
想像力を働かせる
完成されている花の機能美に人間が手を加える。その行為で、人間の根源的な能力のひとつである想像力が養われると渡来は話す。
「今回いけた一杯のように、いけばなは1本や2本という少ない花で空間を満たすことができます。ではなぜ満たせるのかというと、植物そのものの物理的な話ではなく、その一杯が描き出す空間、余白に鑑賞者が想像を膨らませるからなのです。量的な表現のフラワーアレンジメントは、その実体を愛でることで満たされ、余白に想い及ぶことはほとんどありません。現代社会は量的な消費行動がベースにあるので、花を一本いけて楽しむような感性や、余白に秘められた豊かさへの感受性が鈍くなりがちではないでしょうか。合理化が進む世の中で余白はますます埋め尽くされ、それが社会に歪みとして出始めている気がします。私は想像力が日本人の、そして人間の根源的な能力だと信じているから、人の好奇心を刺激し、想像力を働かせるきっかけとなる花をいけたいと考えます。鑑賞者が、『今の私は何を想うのか?』を自問するための鏡のような花を」。
神への祈りとして始まったいけばなはさまざまな時代感を反映して、個性の表現や癒しの対象として求められてきた。現代は社会の発展を求めて合理化が進み、白黒をはっきりさせる風潮がますます広まっている。だがそんな社会に息苦しさを感じ始めている人がいるからこそ、安らぎや変化を求めていけばなを始める人もまた増えている。きっとそれは、花をいけるという行為が余白に想像力を働かせ、心の豊かさを取り戻せると日本人の本能が訴えているからではないだろうか。
「例えば美術館に行ったときに、作品を観ているよりも説明文を読んでいる時間の方が長い人がいる。作品のことを理解するために読んでいるわけですが、それは文章を頭で処理しようとしているだけで、作品に向き合ったといえるのか。本質は作品に内側にこそあるのではないか」と渡来は話す。ここでは彼が過去にいけた花を紹介する。作品に向き合って何かを感じ取り、考え、そして余白に想像力を巡らせてほしい。




渡来徹花道家、いけばな教授者。いけばな教室「Tumbler & FLOWERS」の運営やイベント空間での装花やポップアップなど、いけばなの魅力を幅広く伝えるべく精力的な活動を行う。
| Photo Yuto Kudo | Interview & Text Yutaro Okamoto |