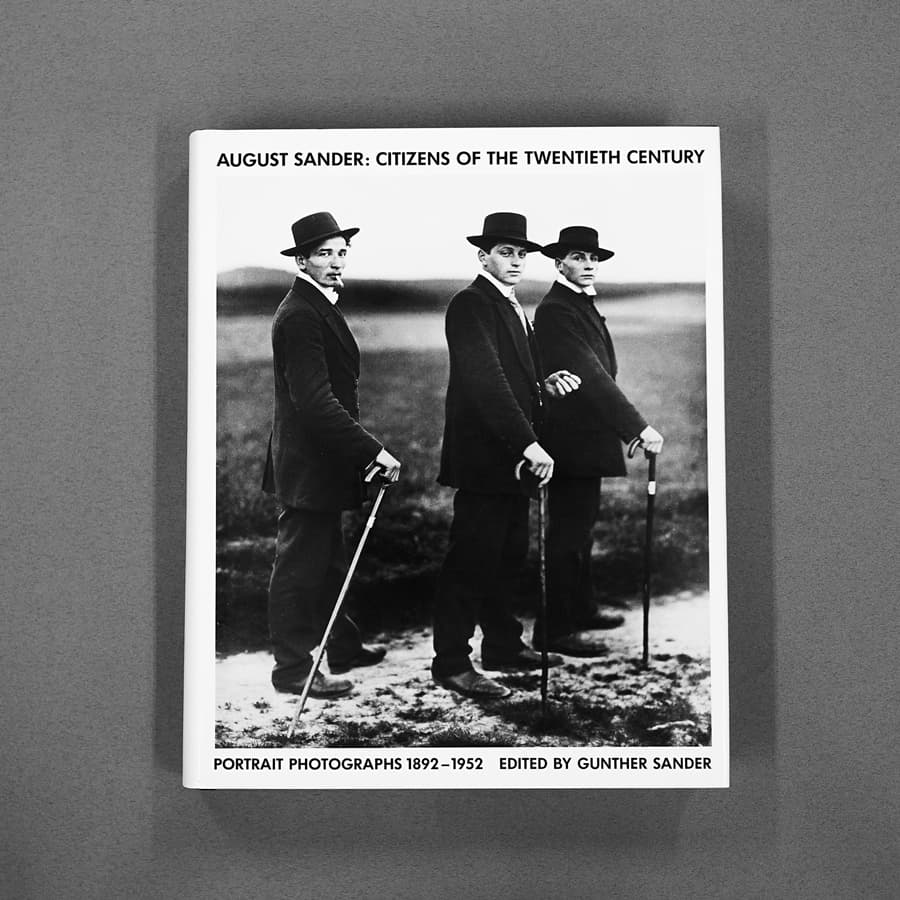Before End of Photography. Talk with Masanobu Sugatsuke and Takuya Chiba
菅付雅信の新書籍『写真が終わる前に』 Silver編集長 千葉琢也との番外トーク

「自分は紛れもなく重度のイメージ・アディクト(中毒)だ」。そう自身を称するのは、編集者として40年近くさまざまな“写真”と関わり、そして目に焼き付けてきた菅付雅信。膨大な量と質の高い写真を見てきた経験から本質を突いた写真批評を多くのメディアや書籍で発信してきた彼だが、この度待望の新書籍『写真が終わる前に(玄光社)』を刊行した。これは写真専門誌『コマーシャル・フォト』で菅付が連載する『流行写真通信』の過去6年分(それ以前の同連載内容は、同氏の別書籍『写真の新しい自由』にてまとめられている)を加筆修正した内容。写真家、映画監督、メディアアーティストなど様々な角度から写真に関わる総勢116名への取材や、写真の時代感から写真エージェンシーの動向まで幅広いテーマを扱った圧巻のボリュームは、写真に興味を持つ人もそうでない人も楽しめる構成になっている。そんな新書籍の発売を祝し、かねてから菅付と親交の深いSilver編集長 千葉琢也との2人による対談を行った。書籍の番外編としてSilver WEBにて一部始終を公開する。

(右)菅付雅信
編集者 / グーテンベルクオーケストラ代表取締役。アートブック出版社ユナイテッドヴァガボンズ代表や東北芸術工科大学教授も務める。『コマーシャル・フォト』の連載「流行写真通信」の本著掲載内容より以前の内容をまとめた書籍『写真の新しい自由』(玄光社)や、『WWD JAPAN』のファッションを巡る連載をまとめた『不易と流行の間』(平凡出版)など多数の書籍を執筆する。
(左)千葉琢也
ファッションカルチャー誌『GRIND』と『PERK』の編集長を歴任し、自身で立ち上げた会社THOUSANDにて雑誌Silverを編集発行する。昨年ファビアン・バロンがアートディレクターを務めたTomo Jidaiの作品をアーカイブした写真集『SESSION WORK』の編集も手がけた。
写真ってなんだ?
ー『写真が終わる前に』というタイトルについて教えてください。
菅付 10年ほど前からデジタルカメラが一気に普及し始めましたが、ここ6年ぐらいでデジタル化がさらに加速しました。それは写真を撮る道具だけでなく、写真を見る道具やメディアにおいてもです。写真の露出先が印刷物からデジタルデバイスにシフトチェンジしているので、逆算的にデジタルカメラを使う流れが起こっているとも言えます。もちろんフィルムカメラにこだわっている写真家もまだまだいますが、商業写真家に関しては9割以上がデジタルカメラで撮っているといえるでしょう。そういう意味では、写真を撮ることの入り口と出口が変わりましたね。
千葉 書籍のタイトルはまさにそういうことを指していますよね。写真って何なんだ?と。
菅付 まさにそうです。
千葉 最近、とある写真家と若いアートディレクター(以下AD)の間で起きたやり取りで面白いなと感じた話が最近あったんです。写真家は自身が撮ったものを写真と呼ぶのですが、若いADが“画像”と呼んだらしいんです。写真を撮る写真家と、画像処理をするデザイナー。同じ一つの像を扱っているのに、写真と画像という異なる捉え方をするんですね。フィルムカメラでプリントしたものは写真という表現に限りなく結びつくと思うのですが、例えばフィルムカメラで撮影してデジタルデバイスで見るものは写真なのか画像なのか?自分は雑誌作りや広告制作をしていますが、コマーシャルフォトは写真的である必要があるのかどうかといったことなどはすごく考えさせられますね。
菅付 メディアの歴史としては写真の大転換期です。このままだと本当に写真が終わってしまうのかと。欧米ではすでに10年ほど前から「End of Photography」という表現で考えられてきた問題でもあります。商業的な領域では動画が主流になってきていて、高解像度でパンフォーカス(近くのものから遠くのものまでピントが合った状態)が求められがちです。スチール写真に関しては動画からの切り出しで補う方法も多いですよね。商品をはっきりと見せる意味では最高ですが、逆にいうとなんのミステリーやロマンも感じない。受け手がイメージを解釈する作業が世の中的に急速に減ってきていると危機感を覚えます。
千葉 僕も広告のお仕事はよくしていますが、その問題についてはよく考えさせられます。正しく伝えることと魅力的に伝えることのどちらをクライアントは求めているのか?と。本来は後者のはずですが、現場のやり取りは常に前者になり、写真的な魅力はどんどん薄れていく。

動かないからこそ想像の余白がある
ー動画の勢いが増していますが、改めて写真の魅力をどう考えますか?
菅付 写真は動かないから動画と比べて情報量が多くない、という人たちがいますが、動かないイメージである、ということに写真の価値があると思っています。なぜなら想像を膨らませる余地があるから。たとえば今東京の街を歩けばデジタルサイネージの広告が溢れていて、動いたり語りかけてくる動画イメージの洪水状態です。カメラ目線のイメージはスチールですら圧がありますが、デジタルサイネージの動画になるとさらに圧や語りかけが強まり、向こうから全てを説明してくる感覚です。だからもはや受け手側がイメージを読み解く隙間もないなと。
千葉 動くことで全て説明できてしまいますからね。人物のポートレートにしても、動かないからこそその一枚が撮影された瞬間の時間や空気、写真家との距離も完全にはわからない。でもそういう曖昧な余白部分が「写真に引き込まれる」という表現として語られるのだと思います。この表現の意味するところが写真と動画の大きな違いかもしれないですね。想像の余白があるかどうかです。
だから今にも動き出しそうだったり、何の瞬間が切り取られたのかを想像させられる写真はおもしろいですね。この数年でいうとジェイミー・ホークスワース(以下ジェイミー)の写真はまさにそういうイメージです。彼は動かないイメージを撮る写真家であることを突き詰めているからこそ、三脚を立ててカメラを固定した状態でしか撮影しないんですよね。しかもデジタルではなく中判フィルムカメラにこだわっているので、狙った瞬間をバンって一枚しか撮らないわけです。そのスタイルは非常に写真家的だと思っています。


ハイとロー
リアルとファンタジー
菅付 写真の不便さが語られるようになっているのですが、その不便ささえ魅力だと思うんです。
千葉 写真界で成功している人は特にそうですが、使いづらかったり制限のあるカメラで撮影することをあえてしていたりしますよね。
菅付 ジョニー・デュフォー(以下ジョニー)に取材をした時に聞いたのですが、彼はデジタルカメラで撮影をしているけど、レンズはわざと質の悪いものを使っているんです。デジタルカメラかつ質の良いレンズだとクリアに写りすぎることが好きではないと話すんです。ほかには、デジタルで撮影した後に紙へプリントして、それをさらに低解像度スキャンをする手法なども用いています。ハイとローを組み合わせて新しい表現を生み出していることがジョニーの面白いところです。世の中のものはどんどんハイスペックに進化していきますが、本当に人はハイスペックなものだけを求めているのか?と問いかけていますね。
千葉 数年前にもフィルムカメラブームが起こりましたが、デジタルネイティブの若い人たちがフィルムカメラを求めるのは、ハイスペックなものに疲れたからという理由もあるかもしれませんね。フィルムの曖昧な部分に落ち着きを感じるのではないでしょうか。最近の車のCMって全てCGで作るらしく、もはや撮影をしていない。それはもう取扱説明書を作るようなことですよね。でも昔の車の広告写真は、フォトグラファーの眼に魅力的に映った角度や瞬間を切り取っていてかっこよかったりする。リアルとファンタジーのギリギリを表現する写真家の見せどころです。
サブジェクトとルック
ー写真家の作家性を読み解く基準はありますか?
菅付 基本的には2つの要素に分けて作家性を読み解くことができると思います。一つ目はサブジェクト、つまり被写体に写真家のスタイルが反映されているか。ラリー・クラークは、映画『KIDS』や写真集『TULSA』など、ユースやドラッグといった自分の身の回りの環境をサブジェクトとして扱っていますよね。山谷佑介は写真家に加えてバンドマンでもあるアイデンティティから、ライブ後のライブハウスやクラブの床の写真を撮り溜めて作品集にしているのもおもしろいです。
要素の二つ目はルック、つまり写真をどう仕上げているかです。ジェイミーの写真は暖色がかっていてルックがはっきりしていますよね。ジョニーのルックもオリジナリティがあります。細倉真弓の青みがかったトーンは、日本人写真家の中でも特にルックが目立っていると言えるでしょう。
良い写真家と呼ばれる人たちは、サブジェクトとルックのどちらかを持っているんです。中でもブルース・ウェーバーやピーター・リンドバーグはその両方を兼ね備えた天才写真家と言えるでしょう。
千葉 アラスデア・マクレラン(以下アラスデア)も両方備えていますよね?
菅付 そうですね。ロンドンのブルース・ウェーバーというところでしょうか。サブジェクトはブルースよりも繊細ですよね。
千葉 どこかクラシックな空気感を持った美男美女のような、一貫性のあるサブジェクトを撮っていますよね。アンバー系の温かみのあるトーンも印象的です。
菅付 アラスデアを取材した時に「どうして成功したと思う?」と聞いたら、「自分ではよくわからないけど、多分俺の写真はウォーム(温かい)だからかな」と言っていました。今は忙しいからトーンを後で作っているようですが、昔は狙ったトーンを生むために陽の光を読んで撮影を組んでいたようです。

社会性あるシグネチャー
ー写真家はサブジェクトやルックが大切ということですが、オリジナリティはどうすれば生まれるでしょうか?
菅付 現代アートはコンテキスト(文脈)を読むゲームだと言われますが、写真も同じです。自分らしさはもちろんですが、何をすれば写真の歴史のコンテキストに対してフレッシュかを意識しながら写真に向き合うことが大切なんです。
千葉 シグネチャーが必要ということですよね。どんな歴史やリファレンスに敬意を払って、それに対する自分の解釈をどう表現するか。コンテキストに対するリスペクトとオリジナリティのバランス感ではないでしょうか。自分のバックグラウンドを突き詰めて考えることがシグネチャーを生み出す第一歩なのでしょうか。
菅付 シグネチャーが強い若手作家としては、ハンナ・ムーン(以下ハンナ)が挙げられます。女性であること、レズビアンであること、韓国出身のアジア人としてロンドンをベースに活動することなど様々なバックグラウンドを個性として、アジア人や女性、LGBTをサブジェクトとしています。これらの要素は今の時代感にも強く結びついているので、彼女はとても社会性の強い写真家です。ハンナとは取材以外でも何度も会っているのですが、時代や社会情勢のある種の代弁者であるという意識を持っています。アジア人で、かつ女性で欧米を拠点に活躍する写真家はあまりいないので、必然的にハンナにインタビューやコメントが求められることが多い。だからこそ発言にはすごく慎重なようで、写真や発言を通して社会の何を代弁すべきかを自覚していることに感心させられます。
千葉 自分は社会の何に向き合っているのかを考えることが今の時代は特に求められますね。タイラー・ミッチェルも社会性の強いシグネチャーを持った写真家だと思います。アフリカ系アメリカ人として史上初めてUS版『VOGUE』の表紙を飾ったのは、アフリカンアメリカンを取り巻く複雑な社会問題を解放するかのような表現にフレッシュさがあるからでしょうか。自分のアイデンティティに向き合った写真家が増えてきていると感じますね。

写真家はスーパークリエイター
菅付 先の動画の話もそうですが、メディアに対して受動的で想像を膨らませる作業が世の中的に少なくなってきています。そんな時代において、アート領域の写真展から写真集の発表といった作家的な活動を行いつつ、一方で雑誌や広告など商業的な面も手がける現代の写真家は考えるべきことが非常に多いわけです。昔のように「商業的に成功したから、そろそろ写真集を出して個展をやるか」という商業的な成功の拍付けのような作家活動は、今は評価されない。ちゃんと現代アートの文脈に乗っ取った作家活動でないと評価されません。それらのアートの文脈を理解し、かつ商業=コマースの流行も理解して、アートとコマースのバランスをとって時代の荒波を超えて活躍する写真家は、現代のスーパークリエイターだと思いますよ。
千葉 いかに人を引き込む奥行きを生み出せるかですね。雑誌を作る編集者としての自分への戒めでもあるのですが、雑誌やファッションメディアこそが写真家と協力し合ってマスターピースとなる作品を生み出さないといけないと思っています。ニューヨークを拠点に活躍するヘアアーティストのTomo Jidaiさんがよく言っているのですが、日本はいい意味でコマーシャルワークが多いと。だからこそコマーシャルワークと同じテンションにするのではなく、もっとエディトリアルに写真家は向かい合うべきだというんです。そのためには僕のような編集者や、写真家をマネージメントするエージェンシーもパワーが必要だとも思います。特にファッション写真に関しては、良い作品というのはスタッフが一丸となってセッションすることで生まれます。90年代の雑誌全盛期を担った写真家のデヴィッド・シムズやマリオ・ソレンティ、ADのファビアン・バロンたちが生み出した写真は今もマスターピースとして残っています。エディトリアルで魅力的な写真を生み出しているからこそ、彼らは現在もなおファッションクリエイティブの最前線で活躍し続けていると言えるのではないでしょうか。
菅付 写真はすごく広くて大きいものだから、そして誰でも撮れるものでもあるからこそ、プロやアートの写真家は、より「頭脳的に」写真を撮って発表していかないといけない。それと同時に見る方も写真を見るだけでなく、“写真を読む力”を持つことが重要です。写真に込められた意図を読み解き、撮った人と見る人の間で暗黙のコミュニケーションが生まれることが写真の醍醐味の一つでしょう。インストゥルメンタルの音楽と同じで、ミュージシャンとリスナーの「俺の意図わかるよね?」「ああ、わかるわかる」というコミュニケーションと同じです。まさに余白のある、引き込まれて読みたくなる写真こそがこれからの時代にますます必要とされるのではないでしょうか。



▼書籍情報
タイトル : 写真が終わる前に
出版社 : 玄光社
発売日 : 2023/1/25
単行本(ソフトカバー) : 306ページ
ISBN-10 : 4768317243
ISBN-13 : 978-4768317242
寸法 : 18.8 x 12.8 x 2 cm
| Photo Asuka Ito | Edit Yutaro Okamoto |